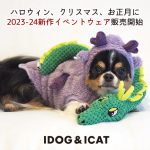猫が爪とぎをしない6つの理由とは?今すぐ実践できる5つの対策も

目次
「あれ、うちの子ぜんぜん爪とぎしない…なんでだろう?」と不安になっていませんか?
猫が爪とぎをしないのは、ただの気まぐれではなく、実は愛猫からのサインかもしれません。
本記事では猫が爪とぎをしない6つの理由と、ご家庭で今日からできる5つの対策を徹底解説します。
可愛い愛猫に関して、少しでも気になる人はぜひ最後までご覧くださいね!
猫はなぜ爪とぎをするの?
猫の爪とぎは、爪のお手入れや縄張りの主張、気持ちの切り替えなど、心と体の健康を保つために行われます。
- 爪のお手入れ
- 縄張りの主張(マーキング)
- 気分転換やストレス発散
- 飼い主さんへのアピール
猫は爪とぎをすることで、爪の表面にある古くなった層をペリペリとはがしています。そうすることで、いつでも獲物を捕らえられるように、鋭く新しい爪を保っているのです。これは、狩りのための爪の手入れという、猫にとって非常に重要な本能的な行動なのです。
猫のぷにぷにした肉球には、ニオイを出す「臭腺(しゅうせん)」という器官があります。爪とぎで柱や家具に自分のニオイをこすりつけて、「ここは私の場所!」と周りにアピールしています。朝起きて「さあ、活動開始!」と体を伸ばしながら、また遊んで興奮した気持ちを「ふぅーっ」と落ち着けたいときなど、気持ちを切り替えるスイッチとして爪とぎをします。ストレス発散にもなりますが、爪とぎをするからといって、必ずしもストレスが溜まっているわけではありません。
飼い主さんの目の前でバリバリと音を立てて、「ねぇ、見て!」「かまってほしいな」と注目を集めようとすることもあります。こんなときは、たくさん褒めてあげると喜んでくれるでしょう。爪とぎは時に、飼い主さんとの大切なコミュニケーションにもなっているのです。
猫が爪とぎをしないのは6つの理由は?
猫が爪とぎをしないのは、性格や年齢、環境などさまざまな理由が考えられます。具体的には、以下のような理由が挙げられます。
- 爪とぎの場所や素材が気に入らない
- 性格がおっとりしている・爪とぎに興味がない
- まだ爪とぎを知らない子猫だから
- 爪が短く必要性を感じていない(爪切り後など)
- 高齢や体調不良で爪とぎができない
- ストレスを感じている
理由1:爪とぎの場所や素材が気に入らない
猫は爪とぎの形、大きさ、高さ、素材(段ボール、カーペット、木、麻など)に対して、強い好みやこだわりを持っています。もし愛猫が爪とぎを使わないなら、その爪とぎが単純に好みではないだけかもしれません。
新しい爪とぎに独特のニオイがして、警戒している可能性もあります。そんなときは、自分のニオイがついたタオルをこすりつけたり、少し天日干ししたりして、安心させてあげると良いでしょう。
理由2:性格がおっとりしている・爪とぎに興味がない
もともとおっとりした性格の猫は、爪とぎをあまりしない傾向があります。逆に、好奇心旺盛だったり、少し怖がりだったりする猫のほうが、気持ちを落ち着けるために爪とぎを頻繁にする傾向にあります。
理由3:まだ爪とぎを知らない子猫だから
おうちに迎えたばかりの子猫が爪とぎをしなくても、心配しすぎる必要はありません。爪とぎを始める時期には個体差があり、早い子では生後1ヶ月頃からですが、一般的には生後12ヶ月頃から始める子もいるといわれています。成長とともに自然と始める可能性が高いので、焦らず見守りましょう。
ただし、壁や家具で覚えてしまう前に、子猫を迎えると同時に爪とぎを用意しておくことが大切です。
理由4:爪が短く必要性を感じていない(爪切り後など)
飼い主さんがこまめに爪切りをして爪が短い状態であれば、猫自身が「爪をとぐ必要がない」と感じて、爪とぎをしないことがあります。
実は、爪とぎと爪切りは役割が違います。爪とぎは爪の古い層をはがすためのもので、爪切りは爪とぎだけでは丸くならない先端を整えるためのものです。定期的な爪切りは続けつつ、爪とぎも促してあげましょう。
理由5:高齢や体調不良で爪とぎができない
高齢の猫(老猫)になると、体力が落ちたり関節が痛んだりして、爪とぎのポーズがつらくなることがあります。おっとりした気質になって、爪とぎをしなくなることも少なくありません。
もし、いつもは爪とぎをしていたのに急にしなくなった場合は、体調不良のサインかもしれません。食欲や元気はあるか、トイレはいつも通りかなどもチェックし、気になることがあれば早めに動物病院に相談しましょう。
理由6:ストレスを感じている
爪とぎの理由の一つにストレス発散があります。そのため、生活環境が整っていてストレスを感じにくい猫は、爪とぎの回数が少ないかもしれません。
しかし、引っ越しなどで環境が大きく変わったストレスで、逆に爪とぎをしなくなってしまう子もいます。愛猫の様子をよく観察して、何か変化がないか、ストレスの原因を探ってあげることが大切です。
もし猫が爪とぎをしないとどうなるの?
猫が爪とぎをしないと、爪が伸びすぎて肉球に食い込んだり、思わぬケガにつながったりする危険性があります。
- 巻き爪になって肉球を傷つける
- 歩きにくくなる
- 爪が折れるなどのケガにつながる
爪とぎは猫にとって、健康管理のための大切な習慣です。もし長い間しないでいると、猫ちゃんが痛い思いをしてしまうかもしれない、いくつかのトラブルが起こる可能性があります。
巻き爪になって肉球を傷つける
爪とぎをしないと、古い爪がはがれずにどんどん分厚くなってしまいます。そして、伸びた爪は内側に巻き込んでいき、やがてぷにぷにの肉球にグサッと突き刺してしまうことがあるのです。そうなると、猫ちゃんが痛い思いをするだけでなく、そこから細菌が入って化膿してしまうこともあります。
歩きにくくなる
爪が伸びすぎると、床やカーペットにカチカチと引っかかって、歩きにくそうにすることがあります。人間でいえば、長すぎる靴を履いて歩くようなものかもしれません。スムーズに歩けないのは、猫ちゃんにとってもストレスです。
爪が折れるなどのケガにつながる
カーテンやカーペット、飼い主さんのお洋服などに伸びた爪が引っかかってしまい、パニックになって暴れた拍子に、爪が根元から折れてしまうような大ケガにつながる危険もあります。
猫が爪とぎをしないときの対処法は?今すぐできる5つの対策
愛猫が気に入る爪とぎを探してみてください。普段から愛猫を観察していれば、「これだ!」というものが見つかりやすくなります。爪とぎの好み以外にもいくつかのコツをご紹介します。
対策1:好みの「素材」を見つける
まずはさまざまな素材を試して、愛猫の好みを探りましょう。猫は素材に強いこだわりを持つため、複数を試すのがおすすめです。
段ボールは安価で人気ですが、とぎカスが出やすいのが特徴です。麻縄やサイザル麻は丈夫で長持ちし、多くのキャットタワーに使われています。他にも木材やカーペット生地などがあるので、愛猫がどんな感触を好むか観察してみてください。
対策2:好みの「形状」や「置き方」を試す
猫がどんな体勢で爪をとぐのが好きかも、とても重要なポイントです。床に平らに置くタイプ、立ったまま使えるポールタイプ、壁に設置するタイプなどがあります。
同じ爪とぎでも、横置き、縦置き、斜め置きなど、角度を少し変えるだけで急に使ってくれることもあるので、ぜひ試してみてください。
対策3:「設置場所」を見直す
猫がリラックスしている場所や、爪とぎをしたくなるタイミングで自然と目に入る場所に置くのが効果的です。例えば、気持ちよく寝ている寝床の近くや、毎日必ず通る廊下、外を眺めるのが好きな窓際などがおすすめです。
対策4:またたびの力を借りて誘導する
どうしても爪とぎに興味を示さない子には、またたびの粉末を少量ふりかけて興味を引くのも一つの手です。爪とぎに良いイメージを持ってもらうきっかけになります。
ただし、猫によっては反応しすぎることがあるので、ごく少量から試しましょう。
対策5:上手にできたらたくさん褒める
少しでも爪とぎを使えたら、すかさず「えらいね!」「上手!」など優しく声をかけ、おやつをあげたり撫でたりして褒めてあげてください。「爪とぎをすると良いことがある」と学習すれば、爪とぎが習慣化されやすくなります。
ただし、あまりにおやつを与えすぎると、おやつのために爪とぎをするようになり、体にも悪影響を及ぼすので、この点は注意が必要です。
壁やソファでの爪とぎをやめさせる方法は?
猫が好む爪とぎを別に用意し、壁やソファは爪とぎ防止グッズで物理的にガードするのが効果的です。
- 爪とぎをされたくない場所をガードする
- より魅力的な爪とぎを近くに置く
- 猫が嫌がるニオイのスプレーを使う
- 爪をこまめに切ってあげる
叱るのではなく、「ここでは爪とぎをできない」「あっちのほうが魅力的」と猫に学習してもらう工夫が大切です。
壁や柱には保護シート、ソファには丈夫なカバーをかけるなどして、物理的にガードしましょう。床を保護するジョイントマットなども有効です。
ガードした場所のすぐそばに、より愛猫が惹かれる爪とぎを設置します。愛猫の好みを観察し、段ボール箱や新聞紙の束など、その子が本当に好きなものを用意してあげることがポイントです。
猫が嫌がる柑橘系のスプレーなども市販されています。ただし効果には個体差があるため、補助的な手段と考えましょう。こまめに爪を切っておけば、万が一爪とぎをされても被害を最小限に抑えられます。
猫が爪とぎをしない理由と対策まとめ
愛猫が爪とぎをしなくても、すぐに心配しすぎる必要はありません。その子の性格や年齢、爪とぎの種類において好みが合わないなど、さまざまな理由が考えられます。
まずは愛猫のお気に入りの爪とぎを見つけてあげることが大切です。どうしてもやめてくれない壁や壁紙は保護シートで、床はジョイントマットやプレイマットでガードしつつ、設置場所も配慮してあげましょう。
猫が爪とぎをしないことに関するよくある質問
Q1:猫が爪とぎをしないのはなぜ?
A1:猫が爪とぎをしないのには、さまざまな理由が考えられます。爪とぎ器の素材や場所が気に入らない、おっとりした性格、子猫や高齢猫といった年齢的な理由、爪切り後で必要ないと感じている、あるいは体調不良のサインという可能性もあります。普段から愛猫の様子を観察して、原因を特定しましょう。どうしても理由がわからず、心配な場合は動物病院で相談するのも有効な手段です。
Q2:猫に爪とぎをさせる方法はありますか?
A2:はい、あります。愛猫の好みをよく観察し、好きな素材や形の爪とぎ器を見つけて、リラックスできる場所に置いてあげるのが基本です。またたびで興味を引いたり、上手にできたら褒めてあげたりすることも効果的です。詳しくは本記事の「猫が爪とぎをしないときの対処法は?今すぐできる5つの対策」をご覧ください。
Q3:子猫の爪とぎは何歳(いつから)始めますか?
A3:子猫が爪とぎを始める時期に決まりはなく、個体差が大きいものです。早い子では生後1ヶ月頃から真似事を始めますが、一般的には生後3〜4ヶ月頃から本格的に始める子が多く見られます。おうちに迎えたその日から、爪とぎ器は必ず用意してあげましょう。
Q4:猫がパンチをしてくるとき、爪が出ていなかったら攻撃的ですか?
A4:爪を出さない「猫パンチ」は、攻撃ではなく、遊びや親愛の情を示している場合がほとんどです。「ソフトパンチ」とも呼ばれ、飼い主さんへの「遊ぼうよ」という誘いや、甘えたい気持ちの表れと考えられます。ただし、猫がしつこくされて嫌がっているサインのこともあるため、表情やしっぽの動きなど、その場の状況から気持ちを読み取ってあげることが大切です。
Q5:今まで爪とぎをしていたのに、急にしなくなりました。病気でしょうか?
A5:必ずしも病気とは限りませんが、体調不良のサインである可能性も考えられます。もし元気や食欲がないなど他の症状も見られる場合は、関節の痛みや内臓の不調があるのかもしれません。心配な場合は、一度かかりつけの動物病院に相談することをおすすめします。
猫の不満サイン見逃してない?愛猫がもっと喜ぶ暮らしを【IDOG&ICAT】
言葉を話せない猫が、ふとした瞬間に送る「不満」や「退屈」のサイン。
あなたは、その小さなサインに気づけていますか?
いつも癒しをくれる大切な家族だからこそ、「もっと幸せで、快適な毎日を過ごしてほしい」と願うのは、すべての飼い主さんの共通の想いだと思います。
大切な家族だからこそ、ささいな変化にも気を配りたいもの。
例えば、あなたの愛猫にこんな様子はありませんか?
- 最近、あまり遊んでくれなくなった…
- 理由もなく、部屋の隅でじっとしていることがある
- 毛づやが悪くなった、または毛玉をよく吐く
- 食事中、むせたり食べづらそうにしている
もし一つでも当てはまったら、それは愛猫からの「もっとこうしてほしい」というサインかもしれません。
このような場合、ストレス発散と爪の健康にも役立つ「爪とぎ」や毛玉対策の「グルーミングブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが、愛猫の暮らしをより豊かにする手助けとなります。
とはいえ、アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。
しかし、あなたの愛猫にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。
なぜ、IDOG&ICATが選ばれるのか。
答えは、33年間ペットの「安全・心地よさ」を追求してきた歴史にあります。
私たちは、元々アパレルの縫製工場でした。その技術と経験をすべて注ぎ込み、「ペットが本当にリラックスできるか」を第一に考えた商品づくりを徹底しています。
愛猫が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。
あなたと愛猫がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?
▶︎愛猫への「ありがとう」をカタチに。IDOG&ICATで特別なアイテムを探す
人気記事ランキング
人気記事ランキング
希少種ミヌエットはどんな猫?性格や特徴、育て方のポイントも解説!
93294views
猫がふみふみする理由とふみふみしない猫との違いとは? #50
65052views
ベンガルキャットが持つ意外な性格とは?しつけは子猫のときから行おう! #115
55132views
アメリカンショートヘアはどんな性格?オスとメスの違いも徹底解説! #77
49540views
猫が急に走り出す7つの理由とは?走る猫の注意点とその対処法も解説! #82
48014views
飼い猫が脱走したらどうしたらいい?探し方と事前にできる対策とは? #48
43381views
ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
36666views
猫のロシアンブルーってどんな性格?「猫ではない」と言われるほどの忠誠心を持つ #129
36561views